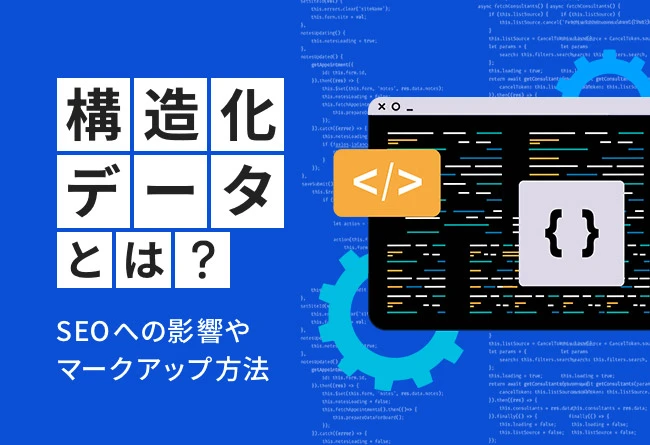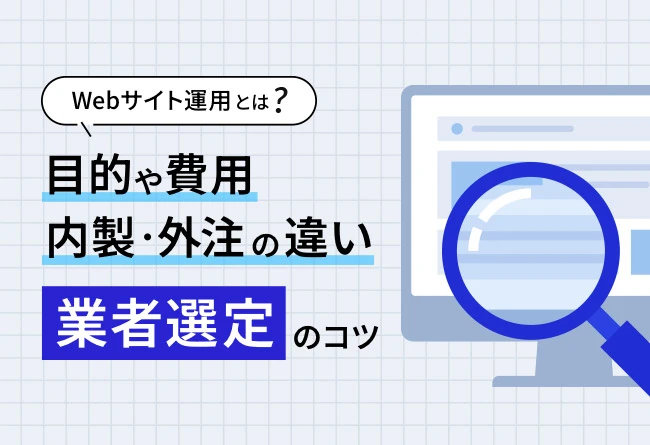これまでのWeb施策では、「検索エンジンで上位を取ること」が自然検索による集客の基本でした。
しかし今、ChatGPTやGeminiといった生成AIの普及やGoogleの「AI Overviews」の実装により、検索行動そのものが大きく変わりつつあります。
すでに多くのユーザーが、従来のキーワード検索に加え、
「この分野に強い会社は?」「この課題を解決できるサービスは?」といった、より深い相談や問いかけを”会話形式”でAIに行うようになってきています。
こうした時代では、AIに“提示・引用される情報”でなければ、ユーザーに発見されることすらありません。
今後は、企業がAI検索への対応をいかに進めるかが、ビジネス成果を左右する重要な要素になっていくと考えられます。
このコラムでは、こうしたAI検索時代に対応する新たなWeb最適化としての「LLMO(大規模言語モデル最適化)」の基本と、AIO/GEOとの違い、企業が取り組むべき具体的な対策ステップなどを、わかりやすく解説します!
目次
LLMO(大規模言語モデル最適化)とは
LLMO(Large Language Model Optimization)とは、ChatGPTやGeminiなどの生成AI(大規模言語モデル)に対して、 自社サイトの情報が正しく認識され、引用されるよう最適化する施策です。
従来のSEOが「検索エンジンでの上位表示」を目的としていたのに対し、LLMOは生成AIに正しく理解・推薦されることにより、 AI検索からの流入や指名検索、長期的には企業やブランドの“第一想起”を獲得することを目指します。 つまりLLMOは、これまでの「ユーザーによる検索」を前提としたSEOに加えて、 AIに“選ばれる存在”となるための、新しいWeb最適化戦略であるといえます。
LLMOとAIO、GEOとの違いは?
LLMOとあわせて語られる関連用語に、AIO(AI Optimization)やGEO(Generative Engine Optimization)があります。 いずれも生成AIやAI検索体験における最適化施策を指しますが、対象とするAIの種類やアプローチには明確な違いがあります。
以下で、それぞれの違いを詳しく説明します。
AIO:AI最適化(AI Optimization)
対象
AI全般:(生成AI/AI検索エンジン/AIレコメンド/AIチャットボット など)
施策概要
AIO(AI最適化)は、生成AIに限らず、あらゆるAIがWeb上の情報を正確に解釈・処理できるように整える、包括的な最適化施策です。
※「AIO」は、Google の「AI Overviews」の略称として使われることもありますが、意味が異なるためご留意ください。
GEO:生成エンジン最適化(Generative Engine Optimization)
対象
生成AI搭載の検索/回答エンジン(ChatGPT/Gemini/Perplexity/Copilot/Google AI Overviews など)
施策概要
GEO(生成エンジン最適化)は、ユーザーが生成AIに質問した際に、自社の情報が正確に参照され、回答文に反映されるよう最適化する施策です。 GEOは、情報を単に理解させるだけでなく、生成AIが“価値ある・信頼できる情報源”として自社を選び、回答に提示されることを重視します。
LLMO:大規模言語モデル最適化 (Large Language Model Optimization)
対象
ChatGPT/Gemini などの大規模言語モデル(LLM)
施策概要
LLMO(大規模言語モデル最適化)は、GPT-4oやGemini 1.5 ProなどのLLM(大規模言語モデル)に対して、自社サイトのコンテンツが正しく理解され、情報源として引用・推薦される状態を実現するための最適化施策です。 AIにとって“読み取りやすく、理解しやすい”構造や文脈で情報を整理・提供することが重要です。
各施策の役割の違い
3つの役割の違いを分かりやすく表にまとめました。
施策名 | 領域の広さ | 役割 |
|---|---|---|
LLMO | 中(LLMに特化) | 大規模言語モデルに情報を「正しく理解・解釈してもらう」ための基盤づくりの施策 |
GEO | やや広い(生成AI出力全般) | 生成AIに引用される際、自社情報が「信頼できる・価値あるもの」として正確かつ有利に出力される確率を高めるための施策 |
AIO | 広い(AI全般が対象) | LLMOやGEOを内包しつつ、生成AIを含むすべてのAIとの親和性を高めるための広義の施策 |
従来のSEO対策とLLMO対策の違い【比較表】
従来のSEOは、GoogleやBingといった検索エンジンで検索結果の上位を目指すための最適化施策です。
しかし現在の検索行動は、生成AIの普及により大きく変化しつつあり、企業サイトの最適化も「AIにどう引用されるか」が重要なポイントとなっています。
LLMOは、生成AIが回答を生成する際に、自社コンテンツが正確かつ信頼できる情報源として認識・引用されることを目的とした最適化であり、 従来のSEOとは対象・目的・評価のされ方に明確な違いがあります。
比較項目 | 検索エンジン最適化(SEO) | 大規模言語モデル最適化 |
|---|---|---|
最適化対象 | 検索エンジン(Googleなど) | 生成AI(ChatGPT、Gemini、Perplexityなど) |
主な目的 | 検索結果ページでの上位表示 | 生成AIに引用され、信頼できる情報源として提示されること |
検索行動 | ユーザーがリンク先をクリックして比較・選定 | AIが回答を要約・推薦(リンク先を提示しないこともある) |
評価軸 | 順位、セッション・PV数、クリック率、CV率 等 | AI回答での推薦・引用数、AI経由の流入数、指名検索数 等 |
SEOは検索エンジンのアルゴリズムに従い、クローラーに評価されやすいサイト構造やコンテンツ・内部リンクの最適化、関連性の高い被リンクの獲得などを中心に行いますが、LLMOはこうしたSEOの基礎施策を活かしつつ、生成AIが参照する学習データや外部記事、構造化データなどを踏まえ、「信頼できる情報だ」と認識されることを目指します。
考え方としては、この2つの施策は競合するものではなく、企業サイトにおいて併せて取り組むべき“セットの施策”として位置づけるのが適切です。
なぜ今、LLMO/GEO対策が必要なのか?
その背景には、生成AIの普及によって検索行動が多様化し、従来のSEO施策だけではユーザーとの接点が限られてきているという現状があります。
たとえば「自社に合った勤怠管理システムを導入したい」と考える企業担当者が、サービスを比較検討しているとします。
従来であれば、GoogleやBingなどで「勤怠管理システム 比較」や「勤怠管理システム クラウド」などのキーワードを入力し、検索結果から複数のサイトを訪れて情報収集していました。 しかし現在では、それに加えて「中小企業におすすめの勤怠管理システムは?」「導入実績が多く、サポートが手厚い勤怠管理システムを教えて」といった質問を、ChatGPTやPerplexityなどの生成AIに直接尋ねるケースが増えています。
このような環境下では、従来の検索上位対策だけでは情報が埋もれてしまい、 “AIに選ばれない=自社を見つけてもらえない”という新たな機会損失が生じる恐れがあります。 特に生成AIは、検索エンジンのように網羅的な検索結果を表示せず、 信頼できると判断した情報から厳選して要約・推薦する傾向があるため、 AIに紹介されなかった企業は、悲しいことに検討候補にすら入らない可能性があるのです。
LLMO対策はどのような企業に有効か?
LLMO対策は、今後すべての企業にとって必要不可欠になると考えられます。 理由は、AI検索は業種や規模を問わず、ユーザーとのWeb接点そのものに影響を及ぼし始めているからです。 中でも以下のような企業では、早期にLLMO対策へ取り組むことで成果が期待できます。
LLMO対策の効果が高い企業の特徴
多店舗展開している企業
例:ドラッグストア、外食チェーン、フィットネスジムチェーンなど
「地域名+サービス名」で検索される頻度が高く、AIによる推奨が来店に直結
BtoB事業を展開する企業
例:IT・SIer、産業機器・製造メーカーなど
比較検討やベンダー選定が多く、“候補の1つ”としてAIに言及されることが重要
BtoC事業を展開する企業
例:化粧品メーカー、家電メーカー、サービス業など
AIが「おすすめ商品」「よくある疑問」への回答として製品情報を引用する機会が多い
海外向け展開を進めている企業
例:日用品メーカー、インバウンド・観光業など
生成AIは多言語・多地域で使われるため、グローバル対応(翻訳・FAQ整備など)の効果が高い
専門性の高い業種
例:医療・法律・金融業界など
専門性や正確性を重視して引用元を選ぶため、信頼性の設計が成果を左右する
BtoB領域ではLLMO対策がより重要に
上記のなかでも特にBtoB領域では、生成AIを活用した情報収集が急速に進んでいます。 サービスの基礎理解、競合比較、ベンダー選定、自社条件に合う候補抽出など、 企業担当者がAIに質問することで意思決定を進めるケースが着実に増えているからです。
こうした変化を踏まえると、製品ページやFAQなどのコンテンツをAI検索に対応させ、“AIに選ばれる存在”になるためのLLMO対策は、今後のWeb戦略の中核を担う取り組みになるといえるでしょう。
「AIに選ばれないサイト」に共通する課題とは?
ここでは、LLMO未対応サイトにありがちな問題をいくつかご紹介します。
- タイトル・Hタグの階層構造が整理されていない
コンテンツの構造が不明瞭で、生成AIが主題や情報の関係性を正しく把握できない。 - 構造化マークアップが適用されていない
コンテンツの構造や意味をAIに正しく伝えるためのマークアップが施されておらず、情報が正確に認識されにくい。 - 文脈が曖昧で、情報の意味が伝わりにくい
話の流れや要点がはっきりせず、AIがコンテンツの意図や結論を正確に把握できない。 - 質問文に対応する明確な回答がない
「◯◯とは?」「◯◯のメリットは?」といった想定質問に対して、明確な結論・要約がなく、AIが回答に活用しにくい構成になっている。 - 第三者ソースでの言及が少ない
外部メディアや第三者記事での紹介が少ないため、生成AIのRAGにおける情報ソースとして扱われにくい。 - エンティティ(実体情報)が未整備
企業名・サービス名・所在地などの固有情報が不足または、表記が統一されておらず、AIに正確に認識・識別されにくい。
LLMOでは、まずこうした構造・文脈・外部情報の整備を通じて、 「AIに正しく理解され、信頼できる情報源として引用される状態」を目指します。
LLMO対策の進め方
とはいえ、すべてを一度に対応するのは負担が大きいため、まずは社内で確認・実行できることから着手するのが現実的です。ここでは、LLMO対策の進め方を4つのステップに分けて丁寧に解説します。
▶ ステップ1:状況把握
自社サイトやサービスの“AIでの見え方”を確認してみましょう。
- GoogleアナリティクスからAI経由の検索流入の状況を把握
- ChatGPT、Gemini、Perplexityなどの生成AIで、自社名・サービス名を検索
例:「〇〇株式会社とは?」「〇〇のサービス内容は?」「おすすめの〇〇サービスは?」 - AIがどのように回答しているかを確認し、誤情報・引用漏れ・重要情報の未掲載がないかもチェック
▶ ステップ2:コンテンツの整理・強化
AIが理解しやすく、引用しやすい情報が整っているかを確認し、 不足があれば、まずはページの更新や修正をしましょう。
- 「基本情報」や「サービス情報」など、サイト内コンテンツが、体系的に整理されているか
- 定義文や概要文が、簡潔かつ明確に記載されているか
- 自社独自の視点や実績、取り組み内容などが、一次情報として具体的に記載されているか
▶ ステップ3:テクニカル対応のチェック
AIに正しく情報を伝えるために、サイト構造やマークアップの状態を把握しましょう。
- ページ構成(H1〜H3など)の見出し階層が整理されているか
- 構造化マークアップ(Schema.org)が適切に実装されているか(FAQやNAP情報など、対象コンテンツに応じて最適化されているか)
マークアップの実装は、エンジニアや制作パートナーに相談のうえ進めることが多いと思いますが、
まずは、見出しの設計やコンテンツ構造が整理されているかを社内で確認することをお薦めします。
▶ ステップ4:エンティティ情報の明記と外部評価の確認
企業やサービスを特定できる情報が明確に記載され、外部メディアなどからの言及が得られているかを確認しましょう。
- サイト内に、会社名・サービス名・業種・所在地などのエンティティ情報が正確に記載されているか
- SNSや外部サイト、メディアで自社に関する発信・言及があるか
自社が「どのような企業か」をAIに正しく伝えるためには、サービスページや会社概要ページの情報を正確かつ最新の状態に保つことが重要です。また、サイテーション(外部からの言及)の獲得はAI評価にも好影響を与えるため、継続的に状況を確認しておきましょう。
どこから始めるべき?LLMO対策の第一歩
前項でご紹介したように、まずは社内で現状を確認することが重要ですが、AI検索で“想起される存在”をいち早く目指したい企業には、プロによる診断サービスの活用をおすすめします。
マイクロウェーブクリエイティブのLLMO診断サービス
当社のLLMOサービス「LLMOde (エルモード)」の現状把握・診断プランについてご紹介します。
現状把握・診断プランの内容
- 構造化マークアップなど、AI向けの情報設計の技術評価
- コンテンツの品質やAI視点での情報の伝わりやすさ・正確さの評価
- 他社との比較による、優先改善項目の抽出
- ChatGPT・Gemini・Perplexityなど、主要な生成AIでの流入状況
- 自社コンテンツがAIに引用されているかや、どのように扱われているかの可視化 など
診断結果は「LLMO診断レポート」としてご提供します。
さらに、診断後のLLMO対策実施〜Webサイト改修まで、貴社の状況に応じたご支援も可能です。
関連サービス:LLMO対策/診断サービス
「まず何から始めればよいか不安」「社内だけでは難しそう」と感じた方は、 簡易的な無料診断も提供しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください!
最後に
本コラムでは、AI検索の進化にともない重要性を増す「LLMO(大規模言語モデル最適化)」について、その基本と、企業が取り組むべきステップをご紹介しました。
コラム内でも述べたとおり、いまや企業のWeb情報は“AIに正しく伝わるかどうか”が問われる時代に入り、従来のSEO対策だけでは、ユーザーに“選ばれる”ことが難しくなりつつあります。
まずは、AI検索における自社サイトの現状を把握し、AIに正しく理解され、信頼される情報設計を早期に整えることが重要です。
当社でも、既存のお客様はもちろん、新たにLLMO対応に関するご相談をいただくケースが増えており、
業種や目的に応じた最適な支援を行っています。
“ユーザーとAIの双方に選ばれる企業”を目指して、今こそ自社サイトのあり方を見直してみませんか?
この記事の著者

マイクロウェーブクリエイティブ マーケティンググループ
「戦略」から「施策まで」企業のデジタルマーケティングに直ぐ活かせる、旬な情報をお届けします。